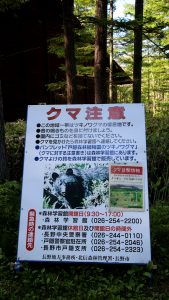今年の夏の繁殖シーズンもどうやら終盤模様にさしかかり、何か無いかなと思案中、戸隠では見ることが出来なかったアカショウビンに逢いたいなと連れあいと意見が一致しました。そんなこんなで急遽アカショウビンに逢いに行こうとなりました。
そして色々とありましたがなんとかアカショウビンに逢うことが出来ました。
アカショウビンが居る場所は薄暗い森の中。撮影はかなり苦労しました。なにせ暗くて遠いのでオートフォーカスは殆ど頼りになりません。こうなるとマニュアル合わせのライブビュー撮影が頼りになりますが、普通の一眼レフでこれをやるのはやはりしんどいなと感じた一幕でした。
それで何とか合わせて撮ったファーストショット。
アカショウビンの右側にある泡みたいなものが、モリアオガエルの卵とのこと。よく見ると卵の上にカエルがいます。これを狙っているんですね。
カエルからみればアカショウビンは天敵になるわけですが、アカショウビンも安閑としてられません。どうやらこの森にサンコウチョウが入ってきたので、それとの確執といいましょうか、縄張り争いのようなものが勃発しているようです。
あまり画質は良くないですが、絵的には凄いことになっていると思います。こんなツーショットはまず普通はあり得ません。写真的にはインパクトはあるかもしれませんが、この(縄張り)争いにアカショウビンが負けてしまうとこれはこれでやっかいなことになりかねないようです。つまり森から追い出されると、今後定着しなくなってしまう可能性があるらしいのです。野鳥同士の争いですから、人が手を出すわけにもいきませんが、なんとも悩ましい話です。
さて、肝心のアカショウビンですが、当然ですが、あまり近くには寄ってくれないので相変わらずライブビューで格闘しながらの撮影になります。
図鑑によるとアカショウビンは雌雄同色となっていてオスメスの見分け方はあまり書かれていません。色々と調べたところ、下腹部が赤褐色のものがオス、白っぽい淡褐色がメスとのこと。
するとこれはメスになるのでしょうか。
そして先ほどのモリアオガエルをとうとう捕食したところ。結構これが残酷なんですね。
ご存じの通り、カワセミなどは捕った小魚をたたきつけて骨を砕いて食べますが、アカショウビンも同じ習性を持っていてこのカエルを散々打ち付けてから食していました。
カワセミの時もそうでしたが、生まれ変わったらカワセミ科の餌にだけはなりたくないと心底思います。ちなみに日本でよく見られるカワセミ類はカワセミ、ヤマセミとこのアカショウビンがいますが、アカショウビンだけが渡り鳥ですね。
そうそう、一瞬ですが、羽をひろげた腰の羽の水色が見えました。
今回はミラーレス一眼が必要だと思いました。特にビューファインダーの性能の良いものがいいですね。管理人はキャノン機を使っていますが、キャノンのミラーレスは初代の物とEFマウントを付けるためのマウントアダプターも持っているのですが、今回は使えませんでした。キャノンのミラーレスは最新の物は外付けのビューファインダーを付けられるようになっていますが、初期型はこれが付けられません。ましてやこれをつけるとホットシューをふさぐので、照準器の取り付けが面倒です。
余談ですが、キャノンのミラーレス一眼はミラーレス一眼しか出していないメーカーと比べると大分機能が劣るので他社のミラーレス一眼の購入を視野に入れざる得ないかと思っていた矢先、このようなデジスコ的な撮影に苦労するとその思いが一層強くなります。なんとかお願いしますよキャノンさんといった心境ですね(苦笑
さて、これから雛が孵るようなので、孵ればもっと活発に動くのではないかと思いますのでこれに懲りずに又行きたいところです。